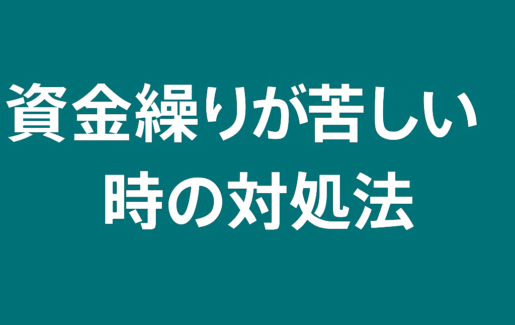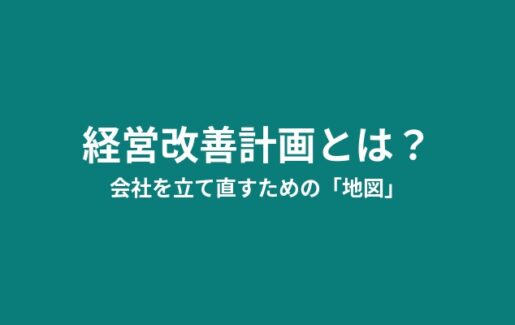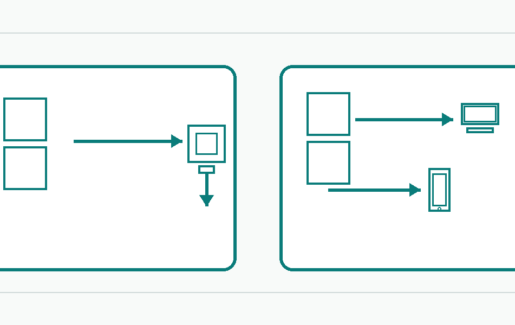財務の計算式を入れると「#DIV/0!」だらけになる会社たち
中小零細企業の決算書をExcelに入力して、財務指標の計算式を入れると──
- 自己資本比率:▲300%
- 債務償還年数:#DIV/0!
- 損益分岐点売上高:計算不能
こんな「エラーだらけ」のシートになってしまう会社は、実は珍しくありません。
ところが現場を見ると、
- なんだかんだで10年以上続いている
- 仕入先・顧客との関係は悪くない
- 毎月の資金繰り表は社長の頭の中にある
つまり、
財務の計算式では「エラー」と判定されるのに、現場ではなんとか回っている中小零細企業が山ほどある
このギャップをどう理解し、どうやって業績改善につなげていけばよいのか。
この記事では、あえて「計算式ではエラーが出る」ような会社に焦点を当てて、決算書の見方・考え方を整理していきます。
なぜ計算式が「エラー」になるのか?代表的なパターン
① 債務償還年数:分母がマイナス or ゼロになる
金融機関がよく見る指標に「債務償還年数」があります。
一般的な考え方では、
債務償還年数 = 有利子負債 ÷(税引後利益+減価償却費)
ところが中小零細企業では、
- 税引後利益がほぼゼロ
- むしろ赤字(マイナス)
- 減価償却も少ない
結果として、
- 分母が小さすぎて「何百年」と表示される
- そもそも分母がマイナスで意味をなさない
- 式をいじると#DIV/0!が並ぶ
という現象が起こります。
② 損益分岐点:限界利益率がほぼゼロになる
損益分岐点売上高も、教科書的には有名な指標です。
しかし、粗利率が低く固定費も高い中小零細企業では、
- 限界利益率(売上総利益率)が極端に低い
- 変動費と固定費の区分が実務上あいまい
その結果、
- 分母が小さすぎて「損益分岐点=天井知らず」になる
- 現実的な水準とかけ離れた数字が出てくる
「売上をあと1.2倍にしたら黒字になります」と出ても、
現場感覚からすると「そんなに簡単に上がらない」という違和感が強くなります。
③ 自己資本比率:マイナスで「見る気がなくなる」
債務超過状態にある中小零細企業では、自己資本比率がマイナスになります。
たとえば、
- 総資産:5,000万円
- 純資産:▲1,500万円
この場合、自己資本比率は▲30%。
健全性評価どころか、見た瞬間に「ダメだ」と言われて終わりです。
しかし、
- ここ数年で売上はじわじわ回復
- 粗利も少しずつ改善
- 借入の返済もなんとか続けている
こうした「回復途上」の姿は、単年度の自己資本比率だけでは見えてきません。
「エラーだらけ」の会社は、どう見ればいいのか?
では、こうした中小零細企業に対して、どこをどう見ればよいのか。
Plowでの支援現場で使っている「現実的な見方」をいくつか紹介します。
① 「水準」よりも「方向」を見る
まず大切なのは、指標の絶対値よりもトレンド(方向)を見ることです。
- 自己資本比率:▲40% → ▲30% → ▲20% と改善しているか
- 売上総利益額:毎期すこしずつ増えているか
- 借入残高:ゆっくりでも減っているか
今の数字が悪いのは当然として、
「悪い状態から抜け出す方向に動いているのか」 を見る。
これだけでも評価は大きく変わります。
② 「利益」だけでなく「キャッシュ」を見る
中小零細企業では、利益とキャッシュが一致しないケースが非常に多いです。
- 減価償却費が少なく、利益は出ているのに現金は増えない
- 逆に、一時的な特別損失で赤字だがキャッシュは残っている
こういう会社を見るときは、
- 営業利益のトレンド
- 営業キャッシュフローのトレンド
- 現預金残高の推移
このあたりをセットで追いかけると、実態が見えやすくなります。
③ 「月商×何か」の簡易指標に落とし込む
複雑な式がエラーになる会社ほど、シンプルな指標に戻すと見やすくなります。
- 借入金残高 ÷ 月商 = 何か月分か
- 在庫 ÷ 月商 = 在庫が何か月分たまっているか
- 固定費 ÷ 月商 = 「固定費/売上」の割合
これだけでも、
- 「借入が月商の何か月分なら危険」
- 「在庫が月商の○か月分を超えたら要注意」
といった簡易的な判断ができます。
特に、数字が得意でない社長にとっては、
「月商の何か月分か」で話す方がイメージしやすい というメリットがあります。
④ 「社長の給与」と「会社の利益」を一体で見る
中小零細企業では、社長の給与=実質的な利益の取り分です。
それなのに、決算書上はわざと利益を減らしているケースも多い。
このときは、
- 会社の利益 + 社長の手取り(役員報酬)
を合算して、
「このビジネスモデルはトータルでどれくらい稼いでいるのか?」
という視点で見ると、構造が見えやすくなります。
計算式は「現実を追い出すため」ではなく「現実を整理するため」に使う
ここまで読んで、
- 「じゃあ財務の計算式なんて意味がないのでは?」
と思った方もいるかもしれません。
しかし、そうではありません。
大事なのは、
「教科書どおりの完璧な数字に合わせるために現実をねじ曲げない」
「現実のぐちゃぐちゃな数字を、少しでも整理するために計算式を使う」
というスタンスです。
たとえば、
- 変動費と固定費の区分を「ざっくり」でも分けてみる
- 売上総利益率が1%でも改善したら、その意味を考える
- 債務償還年数がエラーでも、借入残高と返済原資の関係を別の形で見る
こうやって、現実に合わせて指標の「使い方」を調整していくことが、現場の財務には必要です。
「エラーが出るから見ない」ではなく、「エラーの理由を一緒に見る」
実務で危ないのは、
- 計算式がエラーだから、決算書を見るのをやめてしまう社長
- 債務超過だから、数字の話を避ける銀行・専門家
この状態では、いつまで経っても「なんとなくしんどいまま」です。
大切なのは、
エラーが出るなら、「なぜエラーになるのか」を一緒に分解していくこと。
・なぜ分母がマイナスなのか
・どの費用が重すぎるのか
・どこまで売上が戻れば「エラーから脱出」できるのか
ここまで落とし込めば、「今期やるべきこと」がかなり具体的に見えてきます。
まとめ:エラーだらけの決算書からでも、改善の道筋は作れる
財務の計算式がエラーを吐き出すような中小零細企業でも、
- トレンド(方向)を見る
- キャッシュの流れを見る
- 月商ベースの簡易指標にする
- 社長の手取りも含めてビジネスモデルを評価する
といった工夫をすることで、十分に改善の道筋を描くことができます。
教科書どおりのきれいな数字になってから改善するのではなく、
「ぐちゃぐちゃな今の数字」からスタートして、現実的な一歩を決めていく。
そのためのツールとして財務の計算式を使いこなせるようになると、
中小零細企業の経営は一段ラクになります。
「エラーだらけの決算書」を一緒に読み解きたい方へ
Plow株式会社では、中小零細企業の決算書・資金繰り表を「現場の実態」に合わせて読み解き、
そこから逆算して経営改善計画や資金繰り改善のプランを一緒に作っています。
「数字がきれいでないから相談しづらい…」という状態こそ、お気軽にご相談ください。