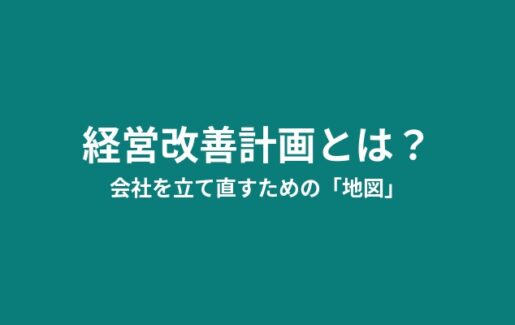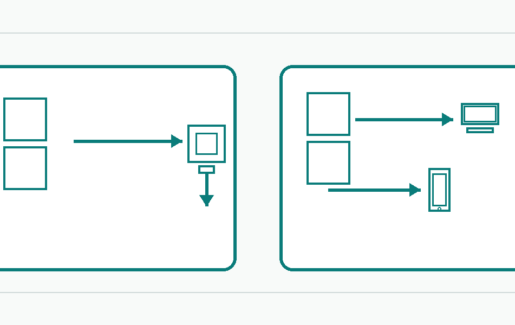税理士でない人間が決算書を作っていた企業の事例
「決算書は毎年できているし、特に問題はない」――そう思っていた企業が、税理士でない人物に決算書を任せていたことで、金融取引や税務の信頼を大きく失ったケースがあります。
本記事では、実際の事例をもとに、発生経緯・問題点・是正の流れを解説します。
1.事例概要:社長の知人が「決算書代行」をしていた
ある製造業の中小企業(年商約1億円)は、あるときから「顧問税理士を置かず」、社長の知人が経理・決算を一手に担当していました。
見た目には毎年きちんと決算書が作成され、税務署にも申告済み。銀行融資も受けられていたため、社長も疑問を持たずに数年が経過していました。
表面上の状況
- 試決算書が毎年提出されていた
- 税務署への申告も継続して実施
- 銀行からの借入も更新されていた
しかし、内部では重大なリスクが潜んでいました。
2.問題発覚:金融機関による「粉飾疑い」指摘
新たに設備資金を申請した際、金融機関の審査で「前年の在庫金額と売上原価の整合性が取れていない」と指摘。
詳細確認の結果、帳簿が税務署提出用に“見た目を整えただけ”で、実際の在庫管理・減価償却計算が適正に行われていないことが判明しました。
しかし、銀行は数字の整合性と信頼性を重視。税理士関与がない決算書は特に疑念を持たれやすいのです。
3.原因:税理士資格のない「経理代行者」が作成
問題となった「経理代行者」は簿記知識を独学で持っていたものの、税理士資格はなく、税務代理権限も税務署届出もない状態でした。
本来、法人税申告書や決算書を外部が作成する場合、税理士法上の制限があり、無資格者による作成は違法行為(税理士法52条)に該当します。
さらに、決算整理仕訳・減価償却・役員報酬設定など、税務判断を伴う処理がすべて経験則で行われており、
正しい利益計算や納税額算定がなされていませんでした。
4.是正への取り組み:税理士・認定支援機関による再構築
対応ステップ
- 過去3期分の決算書を認定支援機関及び税理士が再精査
- 税理士が在庫・減価償却・経費区分の修正仕訳を実施
- 金融機関に上記内容を説明
- 認定支援機関が関与し、経理体制の再構築支援を実施
結果として、粉飾の意図はなく単純な認識不足と判断され、金融機関との取引は継続。
現在は新たに税理士顧問契約を締結し、月次巡回監査を実施しています。
5.教訓:経理・税務は「信頼資産」そのもの
決算書は「融資」や「補助金」「M&A」「事業承継」など、企業のすべての信用取引の基礎になります。
短期的なコスト削減で税理士を外すことは、一見合理的に見えても、将来的な信用損失リスクが極めて高い行為です。
経理・税務は“コスト”ではなく“信頼投資”
正しい数字を継続的に積み上げることが、企業の成長力を支えます。
※設定売上、利益等事例企業は全て事実と異なるフィクションです。
経理体制の見直し・顧問税理士選定のご相談
Plow株式会社では、認定支援機関として、税理士・会計事務所との連携を通じた経営改善体制の構築支援を行っています。
初回相談無料・秘密厳守・オンライン対応可